書籍「ぼくは、イエローでホワイトで、ちょっとブルー」について、内容の紹介と、原稿用紙5枚分の読書感想文を参考例として書いてあります。
読書感想文が苦手な人の参考になればと思います。
※商業利用では使わないようにお願いいたします。(売ったり、講義に使うなど)
©がとーほーむ
本の内容
著者であるブレイディみかこさんと息子さんの体験を基にしたしたノンフィクション(本当の話し)作品です。
アイルランド人の父と、日本人の母を持つ「ぼく」が英国(イギリス)の学校で起こる問題や、多様性についての社会問題に問う話題を痛快な文章で楽しく書かれている物語です。
読書感想文の例
「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」を読んで
○年○組 ○○ ○○
本のタイトルを読んで表紙を見た時、初めに感じたことは、少年野球を題材にしたスポーツ系の小説で爽やかな青春が描かれているのだろうと思っていました。キャップを被った少年がスニーカーの紐を結んでいる姿が表紙に描かれていたので勝手に想像していました。
しかし、本の内容は英国に住んでいる少年の話しです。その少年はアイルランド人の父と日本人の母の間に生まれた子供です。小説かと思って読むと、日本人の母が著者であり、実際に起こった出来事をエッセイとして書かれていた本でした。文章は難しい言い回しではなく、感情が伝わりやすいような普段のしゃべり口調にも近い書き方や表現になっており、その現場にいて一緒に話を聞いているような感覚にもなり、本にのめりこむことが出来ました。「元底辺中学校」や、人の状態を表現に「ファンキー」や「トリッキー」などを使うあたりは状況と気持ちがしっくりと伝わり、口角を上げながら読んでしました。
日本で起こりそうもない、思いもよらないことが次々と起こります。それは、多様性の中に起こる差別や格差と言ったことが生活の中にあるからなのです。
その一つが人種差別です。息子はエリート小学校から元底辺中学校へと進学しました。エリート小学校で落ちこぼれて仕方が無く元底辺中学に進学したのでは無く、エリート中学に行ける実力があるのに元底辺中学に魅力を感じてそちらを選んだのです。小学校の頃は中流階級以上の家庭の生徒が多く、そこでの家庭は人種も様々な人がいたので、人種による偏見がありませんでした。中学校では英国の白人が多く東洋人や黒人などの有色人種は少数派になっており、生徒の中に差別的発言をする人がいるのです。それは、学校でのことだけでなく、町での生活の中でも少なからず起きています。今は人種差別をなくすような考えが政府の政策でもあり、中学校でも問題視して厳格に取り組んでいます。だからこそ『元』底辺中学なのです。今はトップではないが中級に引きあがり個性を引き出せる学校になっています。そこに魅力を感じ息子はこの中学校に進学を決めたのです。
日本では日本人とその他の国籍の人の間で生まれた人のことを「ハーフ」と呼ぶが、そもそも半分という意味なので息子は違和感を覚えている。私はハーフと言う言葉を何の疑問も持たずに使っていた。むしろ、ハーフであることを羨ましいと思ったことすらあります。今ではハーフでなくてダブルと言うこともあるらしいが、息子が言うように「ハーフアンドハーフ」でも良い感じもします。ただし、ネーミングが長いし、ピザのようでも合って日常で使われないと思います。
エンパシーについて考えさせられました。英国ではシティズンシップ・エデュケーションという授業があり(日本でいうと公民教育に近いらしい)そこで、エンパシーについて教育を受けます。息子はエンパシーを問われた回答で「自分で誰かの靴を履いてみること」と書き満点を収めています。私はその回答を読んだだけでは何のことやらさっぱり理解できませんでした。強いて言うのであれば、水虫移るじゃん、くらいの感情しかわきませんでした。エンパシーに混同されがちな言葉にシンパシーがあり、シンパシーとエンパシーの違いについての説明があります。
シンパシーは、誰かをかわいそうだと思う感情。一方、エンパシーは、他人の感情や経験などを理解する能力。つまり、シンパシーのほうは「感情や行為や理解」なのだが、エンパシーは「能力」であり、自分がその人の立場だったらどうだろうと想像することにより、誰かの感情や経験を分かち合う能力とのことです。つまり、シンパシーは共感する感情のことで、自分が努力しなくても自然にできる感情的状態。エンパシーは違い、自分と違う理念や信念を持つ人や、別にかわいそうだとは思えない立場の人々が何を考えているのだろうと想像する知的作業と書かれています。エンパシーは自分で考えなければたどり着かない思考であることが分かりました。
「相手の靴を履いてみること」とは、相手の靴がどんなものなのかを考えること。すなわち、相手が高級革靴なのか、野球のスパイクか、ランニングシューズなのか、おしゃれなスニーカーなのか、使用用途も違うしサイズも様々な靴を履いている人が世の中にはあふれています。相手の立場になって物事を理解しようと受け入れる考えがエンパシーなのです。シンパシー(感情)だけでは拒絶してしまうことも、エンパシーならば容認できるように受け入れる力を身に着けること。それにより人々の確執が解消されるのではないのかと感じました。
まとめ
多様性や差別について、改めて考えさせられる内容となっています。
外国の話しなのかと感じてしまうところもありますが、日本においてもハーフ(ミックス)の人も増えています。
実際に、芸能界やスポーツ界でも増えてきているので、拒絶するのでは無くて受け入れるべき問題なのだと思います。
島国である日本人は外国人を差別していると思いがちで、実際に外国人の悪口を言っている人を見たこともある人が多いのではないでしょうか?
しかし、海外で差別を受けていた人は、日本人は差別しないいい国だとの印象が強いと聞きます。
これは、日本人が差別だと感じているよりも、他国ではもっとあからさまに酷い差別をしていることが分かります。
それだけ日本は安全で住みやすい国ということが分かります。
今後も多様性は拡大していくので、意識して皆が仲良く平和に暮らせる社会を作り上げる意識をしていこう。そう思わせる本だと感じます。
前のページ 「星の王子さま」
次のページ 「きよしこ」
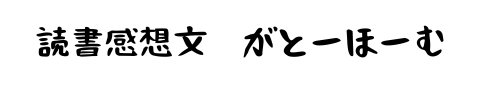
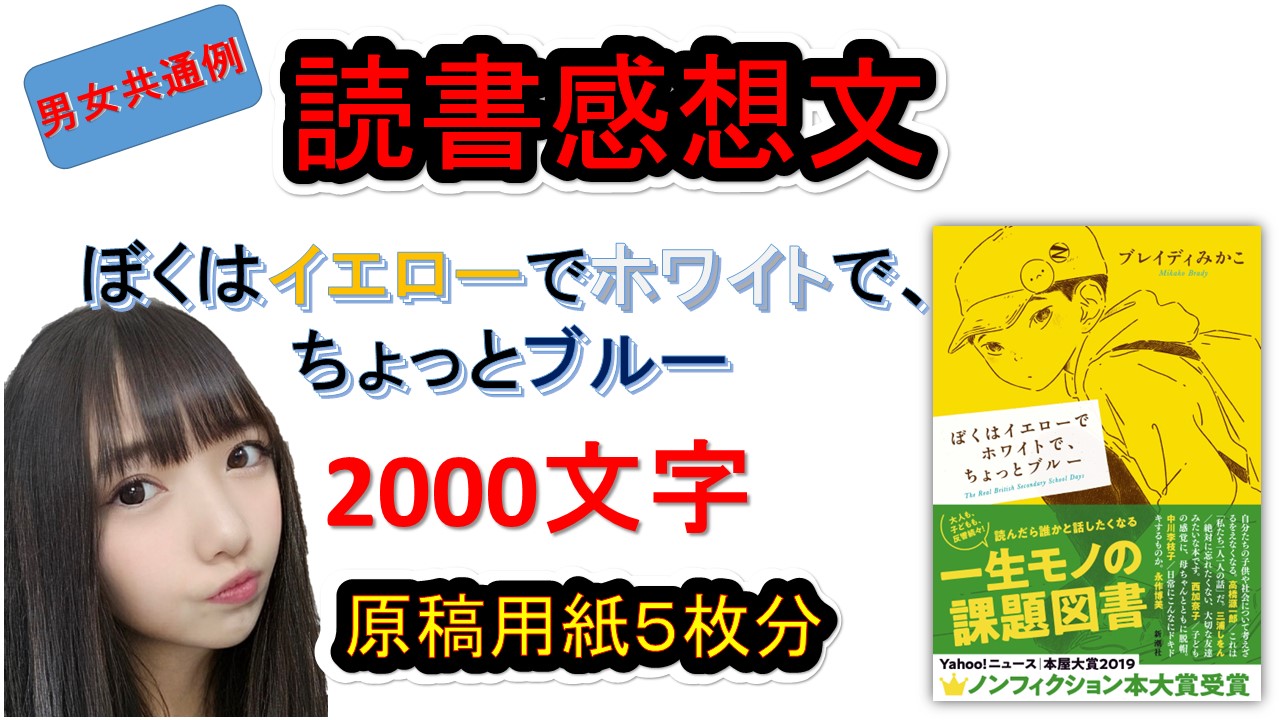

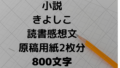
コメント